 白川英樹先生のご紹介
白川英樹先生のご紹介東京工業大学大学院理工学研究科 博士課程修了 工学博士
2000年 ノーベル化学賞受賞
同年 文化勲章受賞
筑波大学 名誉教授
白川英樹先生による記念講演
 白川英樹先生のご紹介
白川英樹先生のご紹介
東京工業大学大学院理工学研究科 博士課程修了 工学博士
2000年 ノーベル化学賞受賞
同年 文化勲章受賞
筑波大学 名誉教授
 私がいつも話をするのは,たぶん,皆さんからすると40~50年前の子どもということです。これだけの,学校の先生をさらに束ねる立場にある教頭先生を相手に話をするというのは,たぶん今回初めてではないかと思うんですが,いささか,どんな話をするかという所からずうっと緊張しておりまして,結局こういう話をすることにいたしました。 私がいつも話をするのは,たぶん,皆さんからすると40~50年前の子どもということです。これだけの,学校の先生をさらに束ねる立場にある教頭先生を相手に話をするというのは,たぶん今回初めてではないかと思うんですが,いささか,どんな話をするかという所からずうっと緊張しておりまして,結局こういう話をすることにいたしました。「知るということ」と関連した「知性」,いろんな言い方をされますけれども,待ち構えた,待ち受けている知性,それと「セレンディピティ」の関係を私の小さい頃のことから話を始めたいと思います。 |
|||
| ◎ | 子どもの頃好きだったこと,学んだこと | ||
| ・ | 小学生の頃,いわゆる理科だったら何でも好きでした。 | ||
| ・ | 中学生の時に昆虫採集・植物採集で野山をかけ歩いていました。 | ||
| ・ | 高校生になっても昆虫採集・植物採集は続けましたが,新たにラジオの組み立てに非常に興味をもちました。 | ||
| ・ | かなり小さい頃から本を読むのが好きでした。この写真(読書中の白川先生)は高山市立第二中学校の図書室で,たまたま友達が撮ってくれたものが残っていました。 | ||
| ○ | 昆虫採集・植物採集をしていると,いろんなことが考えられます | ||
| ・ | 実は昆虫採集だけでなく,卵を採ってきて,そこから卵をかえして,幼虫,さなぎそして成虫,そういう飼育もします。 | ||
| ・ | 昆虫と植物の関係をいろいろ考えると,一方的に昆虫は植物を食べ,逆に,植物は昆虫に食べられるだけの存在かと思っていました。 | ||
| ・ | いろんな本を読んでいて,実は虫を食べる植物があると知りました。その植物を是非採集して栽培し,昆虫を食べる様子を見たいという思いが強くなりました。モウセンゴケです。 | ||
| ・ | 最初に見たモウセンゴケ(の写真)は点眼の白黒でした。カラー写真だと,色が分かるし大きさも分かる。花も花の色とかその他かなり詳しいことが分かります。 | ||
| ・ | 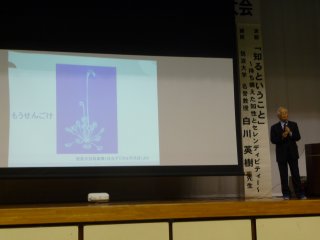 実物は,近所の高等学校の文化祭で,郷土に生えている植物を展示をしていて,その中にモウセンゴケが植わっていて,釘付けになりました。このことを頭に入れて探しに行くと,ちゃんと生えているのが分かりました。 実物は,近所の高等学校の文化祭で,郷土に生えている植物を展示をしていて,その中にモウセンゴケが植わっていて,釘付けになりました。このことを頭に入れて探しに行くと,ちゃんと生えているのが分かりました。子どもながら,その実物を見るということがいかに大切なことか,自然に学ぶことがたくさんあるんだということを学びました。よく観察をする。観察したことを記録する。よく調べて考える。こういうことを整理をします。 |
||
| ・ | |||
| ○ | 観察すればいいというだけの問題ではないと気付かされる大事件 | ||
| ・ | 国立天文台の先生方が,小中高生に天文学に対するアンケートをしました。理科の好き嫌いとか,天文の知識で実施をしました。その中に,小学生を対象に太陽と地球との関係の理解を,いわゆる天動説か地動説,それを正しい方を選ばせたものがありました。 | ||
| ・ | 地球は太陽の周りを回っている,地動説,56%。太陽は地球の周りを回っている天動説,42%にちょうど分かれてしまいました。 | ||
| ・ | 学校は何を教えているんだ。理科教育が崩壊しているんではないか。日本の理科教育はどうなってるんだと,メディアで大きく騒がれました。 | ||
| ・ | 太陽は東から出て西に沈み,月や星も東から出て西に動いていく。本当にそのことをよく見ている子は,天が動いているという,42%のところに入ります。 | ||
| ・ | 小学校の学習指導要領の理科で,天動説とか地動説とかは全く出てきません。中学校では,天体の動きと地球の自転・公転を教えることになっています。高校生になって,やっとここで天動説と地動説の関係のことを教えます。 | ||
| ・ | アンケートをしたのは小学生で,全く教えていない。全く教えていないのに50数%の小学生が正しい答えを知っているのはどういうわけなのでしょうか。いつ,どこで,誰から教えてもらったのでしょうか。 | ||
| ・ | フーコーが,振り子実験によって,地球の自転に合わせて振り子が動くことを見付け,ベッセルが,年周視差の観測によって,地球が太陽の周りを回っているということを見付けました。 | ||
| ・ |  私は,私自身の率直なところ,太陽は地球の周りを回っていると答えた42%がいたのは当然だと思います。自然の観察をして,逆に教えていないのに,本に書いてあるだけ,あるいは親から聞いた。それだけのことで「知っている」と答えたとしたら,これは,むしろ大変なことです。 私は,私自身の率直なところ,太陽は地球の周りを回っていると答えた42%がいたのは当然だと思います。自然の観察をして,逆に教えていないのに,本に書いてあるだけ,あるいは親から聞いた。それだけのことで「知っている」と答えたとしたら,これは,むしろ大変なことです。単に知っているだけではだめで,なぜそうなるのかを説明できるということが必要だと私は思っています。 |
||
| ○ | 自然は解明し尽くされたか | ||
| ・ | 自然の解明は,ほんの少し分かっただけです。自然を見ているとまだ分からないことばかりで,自然というのは宝物の山です。 | ||
| ・ | 私も物理を習ったとき,いろんな法則をたくさん習って,もうこんなに法則が出尽くしているんだったら,もうすることがないんじゃないかと思いました。だけど実際には本当に少し,それだけたくさんでも本当に少しだけだったのです。 | ||
| ○ | 大人になったら研究したかったこと | ||
| ・ | まず1つは,植物採集をして,おいしい果物の品種改良をしたいとか,花を咲かせる植物の品種改良をしたいとかを考えていました。 | ||
| ・ | 2番目は,ラジオを作るということ。私が中学生の終わり頃,ダイオードができました。トランジスタができました。真空管からちょうど切り替える時期で,非常にエレクトロニクスに興味をもちました。 | ||
| ・ | 3番目は化学なんですね。 | ||
| ・ | 普通の自然観察だけだというと,生物と物理学と天文学,まさに自然を観察すればある程度納得がいくけども,自然観察をいくらしたって化学は出てこない。 | ||
| ◎ | 化学を好きになったきっかけとプラスティックの不思議 | ||
| ・ | きっかけは家庭での,ご飯炊き,風呂焚きのお手伝いです。 | ||
| ・ | たき付けで古新聞紙,たとえば魚の干物を包んだ新聞紙に火をつけると黄色い色が出てくる。これは炎色反応だということで,学校の理科室で少しほかの金属をいただいてきたりして炎色反応を楽しみました。 | ||
| ・ | マッチの軸とか木の葉などをビンに詰めて乾留をする,炭を作る。 | ||
| ・ | 私にとっては,マイケル・ファラデーの「ロウソクの化学」を実践しているようなものでした。 | ||
| ・ | 中学校卒業の記念文集に書いた,将来の希望。 | ||
| ・ | 戦争が終わっていろんな新しい物質が出てきました。ナイロンとかポリ塩化ビニール,いわゆるビニール。そのビニールがいろいろ石けん箱とか洗い桶とか,いろんなもので家庭にも入ってきました。その中の1つとして薄いビニールのフィルムを風呂敷代わりで使いました。 | ||
| ・ |  母は,弁当からおかずの汁が出てきても,教科書が汚れないということに気が付いて綿の風呂敷の代わりに,すぐさまそのビニールの風呂敷で包んでくれました。炊きたての熱いご飯をアルミの弁当箱に入れすぐ包むものだから,熱で伸びきる。お昼に食べる頃には冷えて弁当箱に固まってしまっている。次の日に使うため,一生懸命戻すのが大変不便だということに気が付き,欠点を除いた新しいプラスチックを作りたいというようなことを書いたのです。 母は,弁当からおかずの汁が出てきても,教科書が汚れないということに気が付いて綿の風呂敷の代わりに,すぐさまそのビニールの風呂敷で包んでくれました。炊きたての熱いご飯をアルミの弁当箱に入れすぐ包むものだから,熱で伸びきる。お昼に食べる頃には冷えて弁当箱に固まってしまっている。次の日に使うため,一生懸命戻すのが大変不便だということに気が付き,欠点を除いた新しいプラスチックを作りたいというようなことを書いたのです。 |
||
| ・ | 実はこの文集を書いたことは覚えていますが,度重なる引っ越しで,なくなっていました。何とかこれを探そうと思ったけれども,もうどこに行ったか分かりませんでした。ノーベル賞の発表があって,次の日の各新聞に全部これが載っていました。ほかの賞では絶対あり得ない。いかにノーベル賞がすごいかという実感をしました。 | ||
| ◎ | ポリアセチレンの研究と導電性プラスティックの発見 | ||
| ・ | 大学に入って,2年間教養をして,3年目から当初やりたかった高分子化学の勉強をしました。 | ||
| ・ | 幸い大学に残ることになり,そこで始めた研究がこのポリアセチレンの研究です。 | ||
| ・ | アセチレンというものをチーグラ・ナッタ触媒で重合反応すると,ポリアセチレンというものができる。私も仕事を始めたときには,これを作って何とか始めました。 | ||
| ・ | 間もなく,膜に合成する方法が発見されました。しかし,結局これは1000倍の濃い触媒を使ってしまった,失敗実験だったということです。 | ||
| ・ | アメリカのフィラデルフィアにあるペンシルベニア大学の化学科の先生,マクダイアミッド先生にポリアセチレンの薄膜をお見せしたら,とっても興味をもって,アメリカに来て一緒に研究しないかということになり,1976年の9月にアメリカに行きました。 | ||
| ・ | ペンシルベニア大学の物理学のアラン・ヒーガー先生という固体物理を専門にする先生とマクダイアミッド先生,それに私が加わって3人で共同研究を始めました。 | ||
| ・ | ドーピングを使って,電気伝導度の実験を何回も繰り返すうちに,導電性プラスチック,導電性高分子ができることが分かりました。そのことが評価されてノーベル化学賞をいただいたのです。 | ||
| ◎ | ノーベル賞と金メダル 科学と技術 | ||
| ・ | 私が(金メダルに対して)非常に感謝したのは,科学をするという行為を非常に端的に表しているということです。 | ||
| ・ | 左側の女神はナトゥーラ。右側はスケープラで,いずれもラテン語です。 | ||
| ・ | ナトゥーラ(自然の女神)は薄くベールをまとってますが,それを科学の女神(スケープラ)が持ち上げている。なぜ持ち上げているかとこの日に思ったのは,自然をよりよくしようとする知的好奇心に駆られて,自然をよく見ようということ。もう1つは,自然と共存するための知識を得るということ。この2つがちょうど科学と技術に対応しているのではないでしょうか。 | ||
| ・ | 知的好奇心から発する学びが科学。自然と共存するために,いろんな知識を自然から得,自分の身を守るものを作るというものが技術。本来科学と技術は別物であるということです。 | ||
| ◎ | セレンディピティとは | ||
| ・ | 偶然とか失敗がもとで,本来やっていることの途中でそういうことが起こって,脇道にそれた。その脇道の方がより価値がある,あるいは重要な発見・発明になるという考え方・ものの見方とかもある。そういうものをセレンディピティと呼んでいます。 | ||
| ・ | ノーベル賞授賞式2日前の受賞記念講演の後,ノルデン先生(ノーベル賞選考委員の先生)に改めて私たち3人を紹介していただきました。その紹介された言葉が,我々3人は「セレンディップの3人の王子」だというわけです。この物語から「セレンディピティ」という言葉が生まれたということです。 | ||
| ・ | 失敗しさえすればいいのか,偶然に期待したらいいのかというと,そうではなく,ジョセフレンディという人は,「待ち構えた心にだけある」という言い方をしました。 | ||
| ・ | フランスの科学者のルイ・パスツールも同じように言っていますが,彼はまたちょっと違った言葉で,「待ち構えた知性の持ち主だけに行為を示す」です。 | ||
| ・ | プリペアードマインドということになりますけども,あらかじめ身に付けた知性ということで,けっして一夜漬けではない,単に記憶した暗記しただけの知識ではないということが大切です。 | ||
| ・ | ところがセレンディピティの研究家,澤泉重一さんは,いやそうではないんだと言っているんです。それは,偶然を積極的に求めているということに意味があるということです。 | ||
| ・ | 「セレンディピティの探求」~その活用と重層性思考~(角川学芸ブックス),という本の中で彼が書いた部分に,偶然には2種類あり,「やってくる偶然」と「迎えに行く偶然」があるということ。目的意識がはっきりした行動をした結果生じる偶然を,迎えに行く偶然と述べています。 | ||
| ・ | 結局,常識とか決まり切った手順など,当たり前だと思っていることを,改めて疑ってみることが大切です。教科書に書いてある法則についても同じことで,少し疑って調べてみる中からいろんな偶然が生まれてくると言うことです。 | ||
| ・ | 私は,セレンディピティを生まれつきの才能とは思いません。どうしたらセレンディピティを学んでいけるのかというのは,待ち構えた心とか,待ち構えた知性を養うということが大切だと思うわけです。 | ||
| ◎ | 教えない教育 | ||
| ・ | 私はソニー教育財団の主催する「科学の泉-子ども夢教室」の塾長を依頼されて,この14年やっています。全国の小学生5年生から6年生,中1から中2までの生徒約30人を集めて,8月の上旬,お盆が始まる前,5泊6日でしています。 | ||
| ・ | さらに現役の小中学校の先生方にも指導員として応募していただき,居を共にしながら自然観察や実験などを体験するということをやっています。 | ||
| ・ |  指導員にお願いする「教えない」ということは,具体的に子どもたちが何か見付けて,これは何だってたぶん聞く,聞いたときにあまりうんちくを傾けないでほしいということ。興味を抱いたりそんなことを見付けて始めて見たとか驚いていることなど,子どもたちの一瞬の共感を通じて,自然をより深く学ぶ意欲を深めることが目的なのです。 指導員にお願いする「教えない」ということは,具体的に子どもたちが何か見付けて,これは何だってたぶん聞く,聞いたときにあまりうんちくを傾けないでほしいということ。興味を抱いたりそんなことを見付けて始めて見たとか驚いていることなど,子どもたちの一瞬の共感を通じて,自然をより深く学ぶ意欲を深めることが目的なのです。 |
||
| ・ | 指導員は,危険がないようにと目配りをすると同時に,子どもと一緒になって自分もしながら,面白そうだからこんなことやったらどうだろうと,子どもたちにかぐわすというふうにしてほしいとお願いしています。 | ||
| ・ | レイチェル・カースンという人が書いた「センス・オブ・ワンダー」は,とてもいい教科書になるのではないかと思っています。彼女は「沈黙の春」を書いて,自然破壊,農薬とか公害による自然破壊を訴えた人です。 | ||
| ・ | 彼女に小さな甥っ子さんがいて,アメリカの東海岸の自然を一緒に見て歩くということの中で,きれいに花が咲いていたり,何か生き物がいたりすると,一緒になって興味深く見るだけ。決してその動物の名前とか,どういうことかというのも教えない。でも後で甥っ子さんがずっと大きくなったときに,彼は小さいときに見た生物なり植物なりのことをちゃんと調べて,覚えていたことがいろいろ書いてあります。 | ||
| ・ | 科学の泉に理科好きの子どもたちが集まると思っていたらそれだけではなくて,絵を描いたり,いろんな特技がある子どもたちが集まっていて,結局は子どもたち同士で考えて教え合える機会になってるんです。図らずもこの場っていうのは能動的な学修,(「シュウ」は「オサメル」という字を書く),結局は最近よく言われる「アクティブラーニング」がここで実現をしているのです。 | ||
| ・ | 科学の泉は学校教育ではできないことを補完する意味で,教えない教育を一生懸命やっているつもりなんですが,学校教育で全然できないことはなく,何かの手がかりでこういうことを是非始めていただけると思っているんです。 | ||
| ・ | 科学の泉は,夏の5泊6日で終わるのではなく,年に一度,過去の塾生・指導員が集まって交流会をしています。5泊6日の後,自分自身が興味をもったことを自主的に研究したり,発展させている子どもも多く,その研究発表の場にしています。 | ||
| ・ | 教えない教育が,図らずもアクティブラーニングになっているということに気が付いて,こういうことをやっているのは無駄ではないということに気が付いた次第です。 | ||
| ・ | 科学の泉では最後の日に,その5泊6日でやったことをまとめるのではなくて,ここでどんな経験をしたかということをグループごとに発表して,終わりにすることにしています。 | ||
| 今日は「知るということ」~待ち構えた知性とセレンディピティ~ というテーマでいろいろお話ししました。 まとめとして,自然に学ぶ楽しさっていうのは,大自然の中で学ぶ楽しさももちろんあります。だけども「自然に」っていうのは,自ずからとか自らということを大切にするということで,そんな教育を是非実現をしていただきたいということです。 ご清聴ありがとうございました。 |
|||

謝辞