 |
アンリ・ルソーと素朴な画家たち |
 |
 |
 |
 |
 |
笠岡市立竹喬美術館で 「世田谷美術館コレクションによる アンリ・ルソーと素朴な画家たち」展がはじまりました。
2011年11月5日(土)〜2012年1月9日(月・祝日)
開館時間 9:30〜17:00 入館は16時30分まで
休館日 毎週月曜日 年末年始12月29日から1月3日、ただし1月9日は開館
”正規の美術教育を受けず、理論や技法とは無縁に、描きたいという心の衝動に従って作品を創造してきた画家たちを「素朴派」と呼びます”(リーフレット解説より)
ますます厳しい世の中になり、絵を描いたり、趣味に生きる事が難しく感じる今日この頃です。それでも、少なくなったとはいえ、今も世の中には絵を描く人々がたくさんいます。もちろん整備された大学環境、正規の教育(はたして何が正規の教育かはさておき)を受けてという方々もいるでしょうし、一方で美術大学とか専門学校に通う事無くただ絵を描く事が好きで絵を描いている方々もまだまだいるはずです。
なんでもありに思える現代の表現においては、既成の価値観を否定する事によって成立する手法(しばしばそれが革新的と言われたりもする)も重要な表現であり、言い換えれば「理論や技法」として既に確立している存在を訴状に上げ、無理矢理縁を切ろうとするのも表現の一つ。その意識こそ現代と言ってしまえばそれまでなのです。しかし、そんなことを考えるような連中?というのは案外、アカデミックな現場、その傍らにいる人間だったりするわけす。一方、いわゆる世間は門外漢、結果、作られた結果物だけを見て、、、、、、。
もっとも、そういった表現にはそれなりの匂い、ニュアンスがあったりするのが恒で、結局、こういったことを言ったり、書いたりするのもごく内輪の話のようなもの。
さて、最初の素朴派に対する解説について。
制作された作品。何らかの発表行為、また誰かに見せる事が無ければ、それらはなかなか日の目を見る事はありません。どのようにして第三者の目に触れ、評価されるのか?。作品と出会ったおり、多くの場合、世の中の一般的な既成の価値観が評価のポイントになるに違いありません。今時の難しそうな?作品も、うまいヘタから離れた表現をしているとはいえ、、、
裸の王様の話ならずともヘタは、ヘタなのです。
じゃあ 巧いってどういう事?って気になりませんか?
”絵画はかくあるべき”なんてことがすっきり言えた時代、社会ならまだしも、一般的な評価にはある種のルールを決めないと難しくなったのも事実です。
単純に好き嫌い、美醜、、、、趣味、嗜好のあり方。誰しも社会生活、文化歴史の影響を受けてのものもあれば、個人的、生理的な何かが影響してということもあります。いまさらのように美学的な命題と向わないと語れないということになってしまうのでしょうか?
当初、「素朴派」と名付け評価したのは、評論家、画商、画家たち、所謂業界、プロの人達でした。発見は、専門家によって行われたのです。
言い換えれば、それまで世間では評価されていなかったわけです。
専門家には意味が感じられる何かの存在。
それは、理論でもないし、技法でもない。
世の中には多くの絵を描く人がいます。評価される人もいれば、評価されない人もいる。はたして違いを生んでいるのは何か?。それとも、もともと積極的に評価しようとする事が自体が無意味なのでしょうか。
「生命の輝き」と言ってみたり、「エネルギー」「パワー」の存在と言ってみたり、確かに何かを感じるけれど、説明するのは難しそうです。では、一見どうでも良い様な存在にされた感のある「理論や技法」は、誰にでもわかるようなメリット、何らかの意味があったから一般的な価値観になり得たに違いありません。
絵画における技術の役割
わかって当たり前?のことを逆説的に確認することで、本当に大切な何かに焦点があてられないか、、、。そんなことを思っています。キーワードは
<他の人と繋がる事・コミュニケーション>。
素朴派の代表として取り上げられることの多いルソーは、技術とか理論をいいかげんにしていたわけでは無いと聞きます。制作されてから年月を経てもなお堅固な画面、材料の使い方、絵の具の濁りの無さなどは、まさしくそのことを教えてくれているようです。自分で自分自身のことを「素朴派」なんていううさんくささ。描いている本人は、きっとそんな事意識していないに違いありません。
今回も美術講座を仰せつかっています。
11月13日 13:30〜15:00 竹喬美術館視聴覚室 (要申込)
「日本画家の見る素朴派 絵画における技術の役割」
|
|
 |
 |
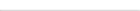 |
 |
|