 |
リアパネル
2つのBNC-Rは
1.受信機に接続するアンテナ端子
2.VFO接続端子
GTソケットには、受信機のスタンバイ配線も出ています |
 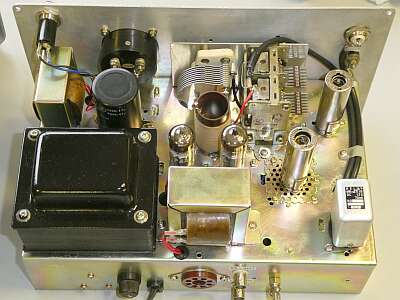 |
シャーシ上部
シャーシは再メッキしてあります
RF系の球には、オリジナルには無いシールドケースが採用されています
整流管 6CA4(黒のブロックコンデンサの位置にあった)は、ダイオードに置き換えられています
元々ブロックコンデンサの取り付いていた位置には、リレーが取り付けられています(右下のシールドされて見える) |
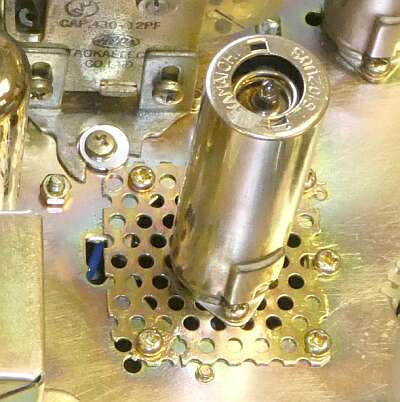 |
終段の6AR5は、対流(放熱)をよくするためにでしょう、パンチングメタルが採用されています
6BM8プッシュプルの変調器は、6AR5シングルには大きすぎるようにも思えます
2E26など、高出力のものに交換して使うことも、想定にあったのかもしれません |
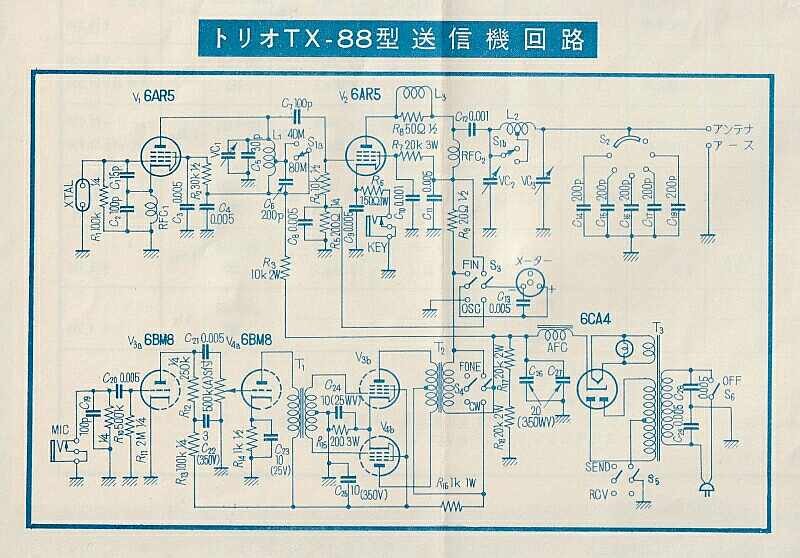 |
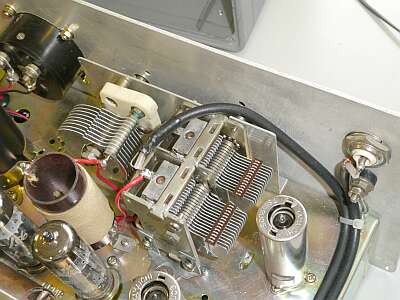 |
シャーシ上部、フロントパネル裏です
VCの取り付けには、サブパネルが用意されていますが、ひとつ横に移動させてあります
メータの位置は、元々200PFロードVCの位置
元々200PFの固定コンデンサを切替るロータリーSWの位置なのですが、430PF2連のVCを取り付けて使用することで、このローターリーSWを省略してあります
VC200PF+必要な容量をSWで切り替えて追加というスタイルを430PF2連VCに置き換え、ツマミをひとつ省略、空いたスペースにメーターを取り付けたという形です |
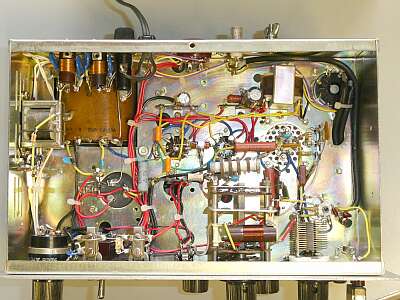 |
シャーシ底側
オリジナルにはなかった、ACラインフィルタが用意されています(電源トランスの上に見えます)
|