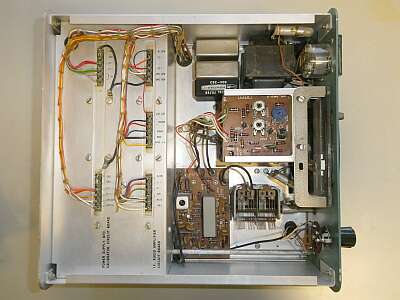 |
外ケースから中身を取り出した様子
トップ側
Heath製品は、アルミニウムシャーシの採用で、年数が経過しても錆びることなく綺麗です |
 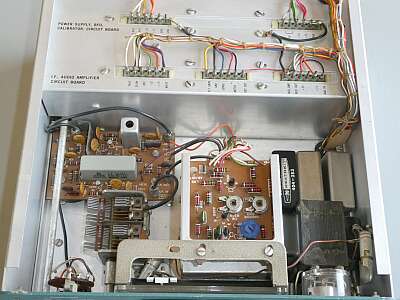 |
上部には、基板が差し込まれるソケットが並んでいます
クリスタル・フィルタですが、SSB・CW・AMフル装備です(CW/AMフィルタは、元々オプション)
同調VCは、RF同調用
その上に見える基板は、
1st-MIX/2nd-MIX部です
基板上のグレーの容器?は、8.4−8.9MHzのBPFです
左端に見えるシャフトは、HF−VHF-CONV切替SWに繋がっています(ANT入力切替) |
 |
トップ側前側です
中央LMO(VFO)の上に載せてある基板は、RTTY検波用
照明ランプは
メーター、メインダイヤルの左右の計3個が配置されています
|
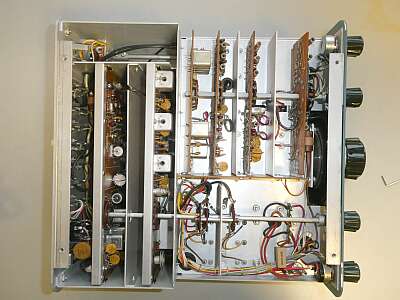 |
外ケースから中身を取り出した様子
ボトム側 |
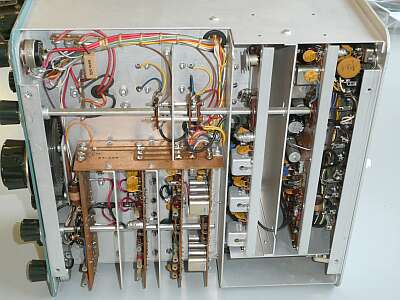 |
ボトム
リア側から
BFO−電源−マーカー基板
IF−DET−AF基板
下に見えるのは
フロント側から
ANT入力基板
RF基板
局発基板
中央に見えるプリント基板は、いわばRF部のマザーボードです
|
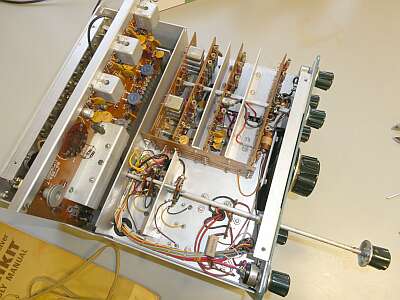 |
ボトム
モードSWのシャフトを抜くことで、リアの2枚の基板のメンテができます
同様にバンドSWのシャフトを抜けば、ANT-RF-局発基板のメンテができます
※メンテ
調整については、このような基板の取り外しは必要ありません |
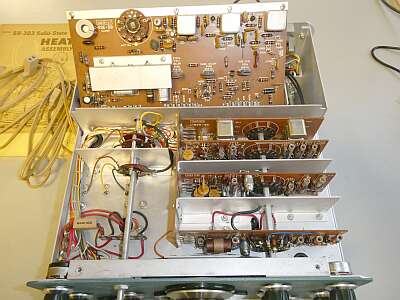 |
ボトム
モードSWのシャフトを抜いて、IF−DET−AF基板を持ち上げている様子
調整以外の基板のメンテには、このような作業が必要になるということです
|